2023年に導入予定であるインボイス制度。経営者はもちろんフリーランスにとっても非常に重要なポイントになる要素の一つです。これは、消費税10%の引き上げに伴ってインボイス制度を導入することが決定されました。
実際に企業や個人事業主にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
今回は、そんなインボイス制度についての概要や、メリットや・デメリット、注意点などをまとめました。反対の声が多いインボイス制度ですが、実際に導入されることになればどんなことが起きるのでしょう。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、日本語で「適格請求書等保存方式」のことを言います。具体的には、個人や会社で発生した請求書や納付書に記載されている年月日や登録番号、消費税額、取引内容などを保存する制度です。
実際に詳しくインボイス制度の詳細についてみていきます。
インボイス制度の概要

インボイスいわゆる「適格請求書等保存方式」は、売り手が正確な適用税率や消費税額などを売り手に伝えるために、区分記載請求書の記載事項に3つの要素を加えたものになります。
つまり、このインボイス制度を用いることで仕入額控除を利用することができるということです。
| 仕入額控除とは? |
|
仕入額控除は、仕入時と売上時とで計算をして収める消費税を計算するというもの。例えば以下の場合で見てみましょう。 A社がB社に対して商品(税抜100万円分)を仕入れたとします。この場合、仕入れた際の請求書には消費税が含まれているため、B社への支払額が110万円となります。ただ、A社はB社から仕入れた商品をC社に商品(税抜150万円分)を売り上げたとします。 この場合、納付しなければならない消費税は売り上げた際に発生した15万円から仕入れ時に支払った際に生じた消費税10万円を引いた5万円となります。 つまり、売上で発生した消費税から仕入れ時に発生した消費税を差し引いた金額が納付額です。この仕組みを仕入額控除といいます。計算式は以下の通りです。 納付額=消費税額(売上時)ー消費税額(仕入時)
|
この仕入額控除が受けられる点において少し厄介になったのがインボイス制度ということになります。
企業においても個人事業主においても経費でかかったお金を経費として認めてもらうために領収書をしっかりと取っておかなければなりません。それと同様に仕入額控除を受けるためにもその証明となる書類を保存する必要があります。
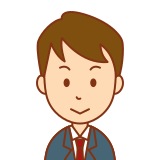
従来の仕入額控除は、取引相手が発行した請求書いわば証拠書類があれば仕入額控除の対象となってきました。
しかし、消費税額の変更から10%と8%が混在するようになり、品目ごとに軽減税率の対象であるかを記載し、税率ごとの合計額を記載したものを請求書に記載する必要が出てきました。これが現在の請求書方式である区分記載請求書等保存方式となります。
さらに、将来は、適格請求書発行事業者の登録番の記載などが必須となってくるインボイスでないと、仕入額控除が適用されずに割高な消費税を納めなければならなくなってきます。
〜令和元年9月 従来の請求書方式(請求書等保存方式)
- 請求書業者の名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 受領者氏名
令和元年10月〜 現在の請求書方式(区分記載請求書等保存方式)
※請求書等保存方式に追加事項
- 軽減税率の対象品目の記載
- 税率ごとの合計金額
令和5年10月〜 将来の請求書方式(的確請求書等保存方式)
- 的確請求書発行事業者の登録番号
- 税率ごとの合計金額及び適用税率
- 消費税額等
ここで問題視されるのが課税事業者と免税事業者です。
課税事業者に与える影響

課税事業者とは、消費税を納付する義務である企業や個人事業主のことを言います。
インボイス制度の対象は消費税納付義務がある課税事業者です。
一般的に売上高や資本金が1,000万円以上の事業者が課税事業者の対象ですが、課税売上高や資本金が1,000万円を超えていなくても課税事業者になることは可能です。
課税事業者にとってインボイス制度を導入しようがしまいが、消費税支払いの義務があることに変わりはありません。
ただ、インボイス制度導入後に課税事業者は免税事業者との取引を減らざるを得なくなるかもしれません。免税事業者との取引では仕入額控除が利用できないためにインボイス制度を活用している取引先へと転換する必要性が出てきます。
そのため、現状で取引相手がどういう状況かをしっかりと把握し、インボイス制度が導入される前にしっかりとした準備が必要になります。
免税事業者に与える影響

免税事業者にとってインボイス制度は、適格請求書を発行することができないために当然消費税の請求ができなくなります。
適格請求書が発行できないとなると何が起こるのか。それは取引の減少です。取引先から適格請求書の発行依頼がきたとしても免税事業者であれば発行ができないため、お断りの連絡を入れざるをえません。
そうなると、課税者からすれば仕入額控除が利用できないため、免税事業者との取引を打ち切りにする企業が増えていくことになるでしょう。
免税事業者は、今後インボイス制度の導入から取引相手の状況を考慮し、なるべく損失の出ないよう免税事業者のままでいるのか、課税事業者になるのかの判断が必要不可欠となってきます。
導入した理由は?

ではなぜ、インボイス制度が導入されようとしているのでしょうか。
その背景にあるのは「軽減税率」です。2019年以降消費税10%に改定され、それと同時に軽減税率が導入されることで8%と10%が混同するようになりました。
10%に変更された後は区分記載請求等保存方式で請求書が発行されてきましたが、ミスや不正を防止すると同時により正確な消費税額を確認する必要があると考え、導入に至っています。
また、益税の排除という面でもインボイス制度の導入理由の一つでしょう。免税事業者は、消費税の納付義務は発生しません。それと同時に消費税込みの請求書を発行することができるため、益税という形で手元に残すことができます。
これらを排除するためにインボイス制度を2023年に導入しようという働きがあるんです。
インボイス制度の廃止を求める声の増加

インボイス制度の導入が見込まれる中で、反対する課税事業者や免税事業者は非常に多いです。
特に免税事業者にとってインボイス制度の導入は不利とだ言われています。課税事業者は、適格請求書発行業者として適格請求書の発行が必要不可欠となる中で、免税事業者にはその発行をすることができません。
つまり、仕入税額控除を受けることができないことになってしまいます。
それと同時に、消費税の余分支払いを避けるためにインボイスを発行できる企業や個人事業主と取引したいと考えるために、仕事が減ってしまう恐れがあることもインボイス制度を反対する理由の一つです。
インボイス制度の導入から、個人事業主は課税事業者に切り替えるべきか、またそのまま免税事業者として働いていくかの判断も問われるところです。
まとめ
今回は、インボイス制度についてご紹介してきました。
インボイス制度の導入から仕入れや売り上げ含め、適格な金額での取引が可能になる一方で課税事業者や免税事業者に大きなデメリットが出てくる可能性もあります。
そのため、取引相手を考慮した取引を慎重化させなければいけないことになるでしょう。インボイス制度が導入する前にしっかりと事前準備をすることが、この制度で生きていくために重要になっていきます。









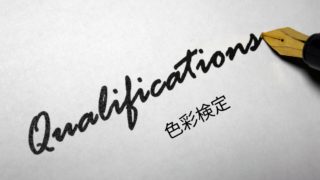









コメント