コロナを機に株式投資を新たに始めた方は多いのではないでしょうか。
株式投資では割安の株を買いたいですよね。では、その株価が割安かどうかを判断するためには、何で判断すれば良いのでしょうか。この割安かどうかを判断するために有効的な指標の一つがPER(株価収益率)でしょう。
この記事では、PERについて、初心者でもわかるように解説します。
PERとは

PERは、「Price Earnings Ratio」の略称です。日本語では「株価収益率」となります。
株価が「1株当たりの当期純利益」の何倍の値段で付けられているかを見る指標になります。「1株あたりの当期純利益」を申すこそわかりやすく説明すると、1株で企業が利益をいくら稼いだかを表しています。
「株価」を、この「1株あたりの当期純利益」で割れば、1株で稼ぎ出す利益と株価との割合がわかります。
計算式は次の通りです。
ここで、株価とは1株あたりの株価をいいます。売買単位は100株単位のことが多いですが、ここでの株価は1株単位の価格です。
例えば、1株あたりの当期純利益が87円だったと仮定すると、1株でその年に87円稼いでいることになります。
この時、もし仮に株価が1株あたり87円だとすれば、投資家は87円で株を購入することができ、企業は投資家から株を買ってもらったことで得られた資本金(87円)を使って企業活動を行い、そっくりそのまま87円の利益を稼いだことになります。
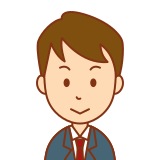
イメージがわかるようにざっくり説明しています。
まあ、まずこのようなことはあり得ないでしょう。基本的には株価の方が高くなります。
ただ、1株で稼ぎ出す利益と株価との差が小さい方が「割安」と言えます。投資した金額に対して生み出された利益が大きいほど優良だからです。安い投資額から高い利益を得られるのがベストですよね。
このようにPERは1株で稼ぎ出す利益と株価との割合を示しています。1株で稼ぎ出す利益を何回転させれば今の株価になるかを表します。
その数字が大きければ、回転数も増え、1株で稼ぎ出す利益に比べて株価が高めの割合であることを表し割高ということになります。
逆に、PERが低ければ、1株で稼ぎ出す利益と株価の差が小さいと言え、割安というわけです。
このように株価に対してどのくらいの利益を稼ぎ出したのかを表しているので、「株価収益率」というんです。
PERの計算方法

PER(株価収益率)は、1株あたりの当期純利益と株価との割合を示したものです。蛇足ですが、株価も1株あたりの価格です。単位は揃えないと比較できませんよね。
PERの計算方法は、
になります。
上の式に出てくる用語「1株あたりの当期純利益」のことをEPSといいます。EPSとは、Earnings PER Shareの略称です。この記事では、「1株あたりの当期純利益」と呼んでいますが、単純に「1株あたりの利益」とも言われています。
次に、EPSを求める計算式は、
になります。当期純利益を発行済株式総数で割ることで1株あたりの当期純利益を算出することができます。
例えば、ある会社の当期純利益が2億円、発行済株式総数が200万株だった場合、EPSは100円となります。
EPSの求め方は理解できましたでしょうか。では、PERの求める計算式をもう一度確認してきましょう。
この計算式に、先ほど説明したEPSを求める計算式を加えてみましょう。
となります。次は、これを変形してみましょう。
これをさらに変形して、
となります。
ここで、注目して欲しいのが、下の式の赤字の部分です。
株価×発行済株式総数とは、つまり時価総額のことです。
時価総額の計算式は、
です。従って、先程の式に時価総額を反映させると、
となります。PERを求める計算式がもう一つできちゃいましたね。
それでは、PERを求める計算式をまとめてみましょう。
- PER = 株価 ÷ 一株あたりの当期純利益(EPS)
- PER = 時価総額 ÷ 当期純利益
この2つの計算式を覚えておけば良いでしょう。
PERの目安とは?

これまで説明した通り、PERは株価が割安なのか割高なのかを示す指標です。PERが高めれば割高、PERが低ければ割安となります。
しかし、割安・割高の判断基準はどうなっているのでしょうか。PERを見ても、それが果たして割安なのか割高なのか判断できないですよね。
PERの目安は、一般的な上場企業で15倍といわれています。
ただし、業界業種によってPERの平均値に違いがあります。令和4年2月23日12時時点におけるデータ(下の表)で比較してみましょう。この表のPER値は予想PERとなっています。
| 企業名 | PER(予想) ※2022年2月23日時点 |
| 東芝 | 13.87倍 |
| シャープ | 7.78倍 |
| パナソニック | 11.55倍 |
| キヤノン | 11.63倍 |
| ニコン | 11.56倍 |
| 資生堂 | 65.97倍 |
| コーセー | 44.78倍 |
| 花王 | 21.37倍 |
| ライオン | 21.36倍 |
| 富士フイルム | 15.97倍 |
| 野村総合研究所 | 32.07倍 |
| 三菱総合研究所 | 11.02倍 |
| NTTデータ | 22.82倍 |
| SCSK | 17.02倍 |
| トヨタ | 11.77倍 |
| スバル | 19.47倍 |
| マツダ | 10.17倍 |
| 日産 | 10.73倍 |
| ホンダ | 9.15倍 |
| ユニチャーム | 32.37倍 |
| エムスリー | 40.51倍 |
| サイバーエージェント | 22.05倍 |
| 武田薬品工業 | 22.2倍 |
適当に会社を抽出して、表にしてみました。これを見るとPERが会社によってバラバラということがわかります。比較的、自動車業界はPERが低い傾向にありそうですね。逆に化粧品業界はPERが高めですよね。あくまでも筆者の主観になりますので、ご了承ください。
ざっくりと紹介しましたが、業界によってPERの基準となる値は違うと思いますので、気になった方は調べてみるといいかもしれません。
まとめ
PERについて説明しましたがいかがでしたでしょうか。PERとは一体どういうものなのかや計算方法について理解していただけたら嬉しいです。
少しおさらいしましょう。
PERとは、1株で稼ぎ出す利益と株価との割合を表しています。
そして、PERの求め方は次の2つの計算方法でした。
- PER = 株価 ÷ 一株あたりの当期純利益(EPS)
- PER = 時価総額 ÷ 当期純利益
一般的には、PERが高めければ割高、低ければ割安と判断できます。
PERが低い・・・割安









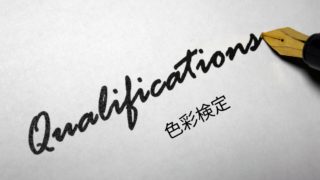









コメント