コロナを機に株式投資などの資産運用に興味を持った方は多いのではないでしょうか。
株式投資ではなるべく割安の株を買いたいですよね。では、その株価が割安かどうかを判断するためには、何で判断すれば良いのでしょうか。
この割安かどうかを判断するために有効的な指標の一つがPBR(株価純資産倍率)でしょう。
この記事では、PBRについて、初心者でもわかるように解説します。
PBRとは?

PBR(株価純資産倍率)は、Price Book-Value Ratioの略称になります。
Priceは株価、Book-valueとは帳簿価額のことで純資産を指します。Ratioが比率や倍率の意味ですので、合わせると「株価純資産倍率」となります。
PBRは、ある会社の純資産に対して株価が適当な水準であるのかを表す指標です。簡単に言えば、株価と純資産との割合を表しています。
PBRを求める計算式は次の通りです。
PBRの単位は「倍」です。PBRとは、1株あたりの純資産に対して株価(1株の価格)が何倍かを表しています。
なぜ純資産と株価の比率を見るの?

なぜ純資産と株価の比率を見るのでしょうか。
それは、会社が解散した時にどのくらいお金が返ってくるのかがわかるからです。
貸借対照表は左側に「資産の部」、右側に「負債の部」と「純資産の部」の3つの区分に分かれています。左右が等しくなりますので、「資産=負債+純資産」が成立するようになっています。
「負債」と「純資産」は、お金を調達する手段です。それに対して、「資産」は調達してきたお金の使い道です。
お金の使い道 ・・・資産
例えば、企業が建物を所有しようと思ったらまずはお金を集めなければなりません。
その方法は、借金するか、もしくは、株主からお金(資本金)をもらう必要が出てきます。この調達方法を表しているのが、「負債の部」と「純資産の部」です。
借金する場合は「負債の部」、株式を発行してお金をもらう場合は「純資産の部」で計上します。
そして、このように調達してきたお金をもとに建物を購入します。購入した建物は「資産の部」に計上されます。
先ほど、調達する手段は、2つしかないと説明しました。繰り返しますが、借金する場合と株式を発行する場合です。
借金する場合は「負債」に計上されます。そして、借金は銀行など人に頼ってお金を集めているので「他人資本」になります。他人資本は基本的に将来返さなければいけません。
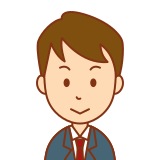
人から借りているので、優先的に返すのは当たり前ですね。
株式を発行する場合は「純資産」に計上されます。株主が出資したお金(資本金)で、返済する必要のないお金なので、「自己資本」といいます。
返ってこないなら、なんで株主は出資するのかと思うでしょう。なぜかというと、株主は会社の成功や成長に期待しているからです。会社がさらに成長すれば株価が上がります。配当金も増えます。
ある会社が突然解散したとしましょう。会社に出資する以上、株主は解散するリスクも想定しておく必要があります。
解散したら、その会社はまず全ての資産を売って、負債(他人資本)を返済します。その後に純資産(自己資本)が残りますよね。「資産-負債」で残った「純資産」は、最終的に株主が受け取ります。
最終的に株主に戻ってくるお金が、出資したお金よりも安かったら損をすることになりますよね。反対に、出資したお金よりも高ければプラスです。
株主は、ある時点で「株価」を払えば株主になることができます。その「株価」と比較して、もし解散したらどの水準まで戻ってくるのかを把握するために「純資産と株価の比率」を見るのです。
PBRの計算方法

PBR(株価純資産倍率)は、1株あたりの純資産と株価との比率を示したものです。
PBRの計算方法は、
になります。
蛇足ですが、株価も1株あたりの価格です。単位は「1株あたり」に揃えないと比較できませんよね。
「1株あたりの純資産」のことをBPSといいます。BPSとは、「Book Value Per Share」の略称になります。
1株あたりの純資産の求め方は、
になります。
純資産を発行済株式総数で割ることで1株あたりの純資産を算出することができます。
例えば純資産が3600億円、発行済株式総数が6億円でしたら、1株あたりの準資産(BPS)は600円となります。
BPSの求め方は理解できましたでしょうか。では、PBRの求める計算式をもう一度確認してきましょう。
この計算式に、先ほど説明したBPSを求める計算式を加えてみましょう。
PBR = 株価 ÷ (純資産 ÷ 発行済株式総数)
となります。次は、これを変形してみましょう。
これをさらに変形して、
となります。
ここで、注目して欲しいのが、下の式の赤字の部分です。
株価×発行済株式総数とは、つまり時価総額のことです。
時価総額の計算式は、
です。従って、先程の式に時価総額を反映させると、
となります。PBRを求める計算式がもう一つできちゃいましたね。
それでは、PBRを求める計算式をまとめてみましょう。
PBRを求める計算式(2つ)
PBR = 時価総額 ÷ 純資産
この2つの計算式を覚えておけば良いでしょう。
PBRの目安とは?

これまで説明した通り、PBRは株価が割安なのか割高なのかを示す指標です。PBRが高ければ割高、PBRが低ければ割安となります。
しかし、割安・割高の判断基準はどうなっているのでしょうか。PBRを見ても、それが果たして割安なのか割高なのか判断できないですよね。
PBRの目安は、一般的な上場企業で1倍といわれています。1倍以上なら割高で、1倍以下なら割安であると言えるでしょう。
PBRが1倍であれば、株価と1株あたり純資産が等しいということです。もし仮にPBRが1倍の時点で会社が解散した場合は、株主に出資した額(株価)がそのまま同額返ってくることになります。※あくまでも理論上の話です。
企業によってPBRに違いがあります。令和4年2月24日におけるデータ(下の表)で比較してみましょう。この表のPBR値は実績PBRとなっています。
| 企業 | 実績PBR ※2022年2月24日中の数値 |
| トヨタ自動車 | 1.17倍 |
| グリコ | 1.04倍 |
| ライオン | 1.69倍 |
| 第一生命 | 0.53倍 |
| ヒューリック | 1.21倍 |
| 三菱地所 | 1.21倍 |
| 野村不動産 | 0.83倍 |
| 良品計画 | 2.12倍 |
| 野村ホールディングス | 0.6倍 |
| コニカミノルタ | 0.48倍 |
| NEC | 1倍 |
| ソフトバンクグループ | 0.82倍 |
| シャープ | 1.66倍 |
| 日立製作所 | 1.4倍 |
| キヤノン | 0.98倍 |
| パナソニック | 0.98倍 |
| NTT | 1.48倍 |
| 楽天グループ | 1.34倍 |
| キリン | 1.79倍 |
| 帝人 | 0.62倍 |
| 三菱電機 | 1.05倍 |
| 東急不動産 | 0.75倍 |
| マツダ | 0.45倍 |
| ヤマダホールディングス | 0.52倍 |
ランダムに企業を抽出して、各社のPBRをあげてみました。大体の会社が0.5倍〜2倍の間に収まっていることがわかります。株価が割高なのか割安なのかを判断するのに、PBRはとても参考になりますね。
皆さんも気になった企業のPERを調べてみてください。
まとめ
PBRについて、理解いただけましたでしょうか。少し復習しておきましょう。
PBR(株価純資産倍率)は、1株あたりの純資産と株価との比率を示したものでした。
そして、PBRを求める計算式は2つありました。
PBR = 時価総額 ÷ 純資産
この2つです。
PBRの目安となる数値は1倍です。1倍より高ければ割高、1倍より低ければ割安といった判断ができます。この1倍の基準はあくまでも目安です。
いかがでしたか。ご自身でも証券アプリや財務報告書を調べて、割安か割高かを判断してみてください。実際に、PBRを求めてみるのもいいと思います。









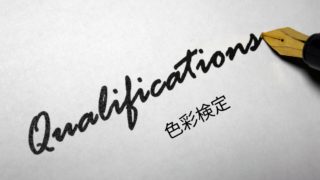









コメント