減価償却は、企業だけでなく個人事業主やフリーランスにおいても重要な会計処理の一つです。減価償却とは、固定資産の取得に伴って発生する金額の適切な金額配分です。
中でも建物や自動車などの有形固定資産は、年数が経つにつれ価値が減少していくもの。例えば、マンションやアパートを想像すればわかりやすいでしょう。築年数が経っているものより新築の方がお金がかかってしまいます。
減価償却は、有形固定資産だけだと勘違いしている人も多いのですが、実は無形固定資産にも減価償却するものもあります。
今回は、減価償却の仕組みや無形固定資産の減価償却などについてご紹介していきます。
減価償却とは
減価償却とは、固定資産の取得に際し全額を費用として計上するのではなく、耐用年数に応じて価値に相当する金額を処理するというものです。
減価償却の処理は、初心者にとって少し難しい処理となりますので、日商簿記を勉強すると理解が深まるでしょう。

減価償却の仕組み
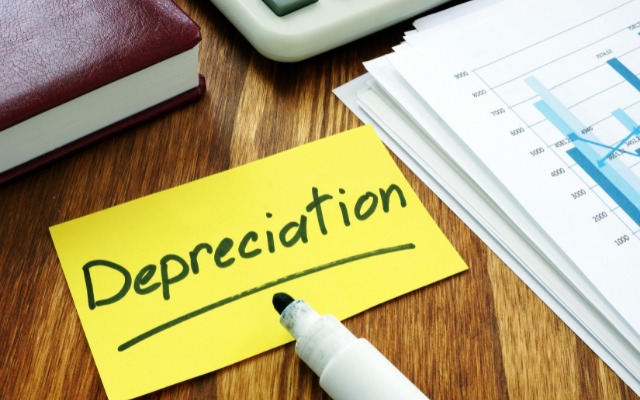
固定資産には、大まかに有形固定資産と無形固定資産の2つに分類されます。有形固定資産とは、自動車や建物といった営業活動に際して使用する形に残る財産のようなもの。対して、無形固定資産とは特許権やのれん、ソフトウェアなど物理的な形態を持たないものを指します。
減価償却は、上記のような有形固定資産や無形固定資産を長期間にわたって経費としての金額を配分して計上するといった形になります。
減価償却の対象となる固定資産は、10万円以上かつ使用可能期間が1年以上というものが原則です。そのような固定資産は、基本的に一括での経費計上することができません。

ただ、上記のような条件に当てはまらなくとも減価償却することができない固定資産が存在します。減価償却できる固定資産とできない固定資産は以下の通りです。
減価償却可能な固定資産
| 有形固定資産 | 建物(ビルやオフィスなど)・工場・備品… |
| 無形固定資産 | ソフトウェア・意匠権・特許権・商標権… |
減価償却不可能な固定資産
| 有形固定資産 | 土地・美術品… |
| 無形固定資産 | 借用権・地上権・地役権…. |
ただし、場合によって少額減価償却資産の特例措置を受けることが可能です。これは、30万円未満の減価償却資産を導入した際に、限度額300万円として全額を一括で処理できるというもの。
ただ、こちらは条件があり、青色申告書を提出している資金額1億円未満の個人事業主・中小企業のみとなります。
なぜ減価償却が必要か

そもそもなぜ減価償却をする必要があるのでしょうか。
毎年莫大な利益を得ている会社や個人事業主なら巨額な影響はないかもしれませんが、減価償却をせずに1年間の売り上げを計上してしまうと、経費分を差し引くことで形上は利益があったとしても、結果的に赤字になってしまうケースが考えられます。
赤字になるとどうなるのでしょう。
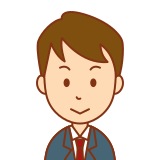
融資を受けれなくなってしまう可能性が高くなってしまうんですね…
そもそも、銀行などから融資を受ける際にその会社や個人事業主の財務状況を把握する義務があります。融資がないと新規事業の開拓も難しく、最悪倒産になってしまい変えません。
そうならないためにも、事業を行う際の固定資産を減価償却することによって毎年の経費を軽減させ、毎年の利益のバランスをとっているんです。
減価償却の計算方法

減価償却を行う際の計算方法は大まかに「定額法」「定率法」の2種類存在します。
定額法
定額法とは、名前の通り金額が均一になるように計算します。
| 取得原価 | 有形・無形固定資産の購入の際にかかった金額 |
| 残存価格 | 耐用年数まで使用した際に残った価値 |
| 耐用年数 | 固定資産を取得した時からどのくらい使用できるかの利用年数 |
ex.
取得原価 600万円の自動車を購入し、耐用年数6年で減価償却を行う。この場合の初年度の減価償却費は、
600万円÷6=100万円
また、初年度に限らず1年後、2年後….と100万円ずつ計上するといった形になります。
主に建物に関する固定資産は定額法が用いられています。また、特許権や商標権などの無形固定資産も基本的に定額法で処理します。
定額法は、計算方法も非常に簡単なために将来の会社の財務情報を管理しやすく、将来の計画が立てやすいという面でもメリットです。
定率法
定率法は未償却残高(初年度は取得原価)を一定の割合を減価償却費として計上するといった計算方法です。定額法と比べて少し複雑な計算方法になります。
取得原価100万円のタイムレコーダーを購入し、耐用年数5年の減価償却を行う。償却率は0.4なので、この場合の初年度の減価償却費は、
100万円×0.4(償却率)=40万円
この場合、2年目では未償却残高が60万円となりますので、60万円×0.4=24万円です。
| 年数 | 減価償却費 | 未償却残高 |
| 1年目 | 40万円 | 60万円 |
| 2年目 | 24万円 | 36万円 |
| 3年目 | 14万4,000円 | 21万6,000円 |
| 4年目 | 8万6400円 | 12万9,600円 |
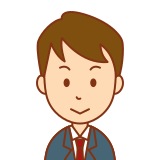
このままの減価償却では何年かかるかわからないですよね
ここで、保証率と改定償却率が重要になってくるわけです。保証率は耐用年数によって定められており、保証率によって計算された金額より下回りそうな年度に改定償却率を使用して減価償却をするといった形になります。
上記の場合、耐用年数が5年ですので、
- 保証率・・・0.108
- 改定償却率・・・0.500
となります。
償却保証額の計算方法は
| 年数 | 減価償却費 | 未償却残高 |
| 1年目 | 40万円 | 60万円 |
| 2年目 | 24万円 | 36万円 |
| 3年目 | 14万4,000円 | 21万6,000円 |
| 4年目 | 10万8,000円 | 10万8,000円 |
| 5年目 | 10万8,000円 (10万7,999円) |
0円 (1円) |
なお、わかりやすい例題により、未償却残高が0円となりましたが、実質には資産を残すために簿記上で1円を残すことになります。これを備忘価格と言います。
なお、減価償却費が改定償却率をかけることで未償却残高を超える場合は、残高が1円となるように調整します。
減価償却のメリット

減価償却のメリットは節税ができること。経費として計上することができるので、利益を抑えることで支払う税金を減少させることが可能です。
また、個人事業主や中小企業は30万円未満の固定資産を計上する際に少額減価償却資産の特例措置を受けられる可能性がありますので、全額を経費として計上することもできます。
さらに、財務状況を把握できることも減価償却のメリットです。高額な固定資産を一括計上するわけではありませんので、毎年の収益への変化をバランスよく把握することができます。
財務状況の把握は経営するにあたって非常に重要なことですからね。
中古品の減価償却はどうなるのか

減価償却の計算方法について上記で解説しましたが、固定資産には法定耐用年数が存在し、その耐用年数に基づいて定額法または定率法で計上していきます。
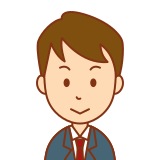
ただ、中古品ってどうなるのでしょうか。
中古品の減価償は、通常の減価償却と考え方は何ら変わりません。しかし、耐用年数が法定ではないことが、通常の減価償却と異なる点です。
その耐用年数は、取得した固定資産の使用期間を合理的に見積もることで算出するといった形になります。いわゆる残存耐用年数ということになります。
あくまでも法定耐用年数は、新品の固定資産を所得した場合の前提であり、中古品にも同じような方法を用いると不合理であると言えるでしょう。
しかしながら、合理的に使用期間を見積もることが困難な場合も数多く存在します。その際には、簡便法という方法で耐用年数を算出することが可能です。
◯耐用年数全てを経過した固定資産
◯耐用年数の一部を経過した固定資産









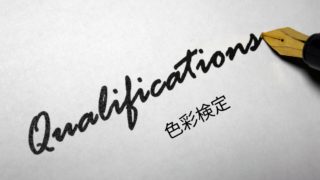









コメント